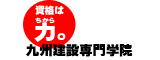合格者の声(合格体験談)
九州建設専門学院で学ばれ見事に「インテリアコーディネーター」を取得された皆様から「お喜びの、感謝の、そして成功の軌跡」が毎日のように事務局に寄せられています。これらの合格体験談は、これから国家資格取得を目指される皆様の励みとなることでしょう。合格者の皆様、誠におめでとうございました。また、ご協力ありがとうございます。


以前から建築関係の仕事に従事しており、仕事の幅を広げていきたいと思いインテリアコーディネーターの資格を取ろうと考えていました。
インテリアコーディネーターの講座は通信教材ばかりで、生講義形式の試験対策をしているところが他になく、1次試験対策でも貴学院にお世話になり、2次試験でもお世話になりました。
試験対策はとにかく数をこなして、作図をすることを心掛けました。貴学院では個別指導で先生からの的確なアドバイスをいただけ、力を確実に付けることができました。お蔭様で合格できました。
これからは地域に密着したビジネスを展開して交流を図り、資格をPRして仕事に活かしていきたいと思います。


短大時代に住居学を学び、図面や家具に興味を持ったことがこの資格取得のきっかけになりました。就職先はインテリアとは全く関係のない業種ですが、家具を見に週末によく家具店に足を運んでいます。そのうちインテリアコーディネーターという職業があることを知り、憧れになりました。資格を取ろうと思った時に貴学院を知り、建設の専門学校なら図面の基礎から学べると考え、入学しました。
実際に勉強をはじめてみると、とても大変でした。1次試験は販売・技術の2科目なので、かなり広範囲の内容で、2次試験では高い技能が求められるため最初から最後まで根気強く学習することが必要です。また家具を含めインテリアが好きなことが大きなポイントとなると思います。私の場合は途中ブランクもあり、足掛け7、8年で2次試験の合格に辿り着きました。
念願の資格に合格でき、自信が付きました。またいろいろなことに挑戦していきたいと思います。


私がインテリアコーディネーターの資格取得をめざしたのは、家業の建築の仕事をする上で役立つと思ったからです。一次試験を受験しましたが1科目が不合格になり、どこかで教わらないとだめだと思いました。その時に貴学院から案内が届いて、興味を持ったので早速学校見学に行きました。1科目だけでも個別指導で教えてくれるとの説明に納得し入学しました。事前の説明通り、講義は私のために戸塚先生が親味になって個別指導をして下さり、大変勉強になりました。
学習のポイントは、問題をくり返しくり返し解くことです。そして、分からない箇所は先生に質問して理解に努めました。
本試験で予想外の問題が出題され戸惑いましたが、今までの勉強のおかげで無事合格することができました。貴学院と戸塚先生には大変感謝しております。
今後は、今回の受験勉強で培った知識を本業の建築の仕事に活用していこうと思います。


元々インテリアに興味があったので資格を取ろうと思い、丁度貴学院でパースを習っていたこともあり、インテリアコーディネーターにも申し込みました。
学習のポイントは、とにかく繰り返して問題を解くことに尽きます。
今月は論文が忙しいため、合格祝賀会に参加できず残念です。12月13日の二次試験に合格するよう努力しております。
山本先生によろしくお伝え下さい。修士論文が落ち着きましたら、学院に遊びに行こうと思っています。


以前から住居に関して興味があり、特に室内に関しては家具などの配置や部屋全体の配色を考えるのが得意だった為、職業にしたいと思いインテリアコーディネーターの勉強をしようと思いました。学院は新聞の広告を見て入学しました。
学習のポイントは、私の場合1年目に一次、2年目に二次とゆっくり時間をかけて勉強しました。お陰様で二次に合格できたので2年以内に2級建築士とインテリアプランナーの資格を取得したいと考えています。
この度はどうもありがとうございました。


他校で一次試験のみの勉強をして合格したのですが、二次の勉強は全くしていなかった為、入学しました。4回の授業で平面図からアイソメ、パースまでポイントを押さえて教えていただき、参考になりました。最後の授業で「今年はパースが出るかもしれない」と先生がおっしゃり、家で何度も練習したことが合格に結びついたと思います。
今、宅建を勉強中で今年は合格を目標に頑張りたいと思いますし、来年は2級建築士も受験できたらと思っています。


私がインテリアコーディネーター資格試験を取得しようと考えたのは、以前から関心が深かったインテリアの仕事を一生していきたいと考えたからです。そのためには、まず資格をきちんと取ろうと学校探しから始めました。いくつかの学校へ問い合わせをしたところ、どの学校よりも事務局の方が親身になって説明をして下さるので、この学院に決めました。
私は木曜日の昼間コースだったため、人数も5~6人と少人数で講師の先生も手取り足取りわかり易く熱心に指導して下さるので、勉強から遠のいていた私でも楽に理解していくことができました。
学習のポイントは、まず理解していくということが大切だと思います。試験は暗記しなくてはいけませんが、暗記するためには理解していなければ頭に入りにくいからです。暗記は自分一人でも出来ますが、理解していくためには、やはり一流の先生に説明してもらうのが一番の早道だと思います。
今後はこの資格を活かせる仕事を見つけて生き生きと働けたらと思っています。
最後に講師の先生はじめ、学院の方々、ほんとうに1年間お世話になりました。ありがとうございました。


「インテリアコーディネーターの仕事がしたい」と、ここ数年間思ってきました。しかし、主婦が急に仕事につけるはずもなく、その足がかりを作るためにも、インテリアコーディネーターの資格は必要でした。
下関では学校に通うには不便ですし、アルバイトをしておりましたので、通信教育を選びました。その際、マンションのモデルルームでのアルバイトのおかげで自分で学費が払えましたし、インテリアコーディネーターの仕事への思い入れも強くなりました。
でも、仕事をしながら、自分で勉強するのは本当に大変ですね。気持ちの問題ですが…。私の場合も勉強を始めたのは仕事をやめた9月1日からです。オシリに火がついていたので必死でした。通信教育のテープは本当に役立ちました。何度も聞きました。ウォークマンをエプロンのポケットに入れ、家事をしながらも聞きました。テキスト、テープ、過去問をひたすらくり返しました。実技はそうもいかず、ゼロから1ヶ月で二次試験に合格できたのは直前の4回の講義のおかげだと思います。藤原先生、山下先生はじめ、スタッフの皆様どうもありがとうございました。


仕事上必要だったので、インテリアコーディネーターの資格にチャレンジしました。貴学院に入学した理由は便利だったからです。
学習のポイントは、11日の目標を具体的に設定する。例えば、10月の試験まであと3ヶ月とすると、その間に問題集を3回解くようにする。1ヶ月に問題集を1回仕上げる。そのためには、1日に○○ページ(又は1週間に○○ページ)を学習するという具合である。2その目標を毎日(又は毎週)達成しないと試験に落ちるという危機感をもって努力する。
講義の時に先生の「(実際の仕事にはあまり役に立たない)こんなものは1年きりで終らせて下さい」という言葉が勉強する際の励みになりました。先生本当にありがとうございました。
今後はインテリアコーディネーターの技能を仕事に活かしていきたいと思っています。


インテリアコーディネーターの資格取得を目指したのは、仕事上必要だったからです。実技の試験は独学で合格するのは難しいと思ったので、どこかで講習を受けようと思っていました。たまたま受験の際に貴学院の存在を知り説明を聞いたら実技だけの受講もできるということだったので、学院に入学することにしました。
講義は、ベテラン講師の中川先生が個別指導をしてくださり、随分勉強になりました。とくに、パースなどは正解がない為、1人で学習するのは難しく、解いた問題を先生に見て的確にアドバイスして頂きましたので、難関の実技試験に合格することができました。中川先生のおかげです。ありがとうございます。
今後の抱負は、インテリアコーディネーターの資格を活用できるよう仕事に励み、さらに仕事に関連のある資格も取得できるように勉強していきたいと思っています。


自分の手を動かして、ものを作るのが好きです。家具を造ったり、素材にさわったりしていました。インテリアコーディネーターには自宅を建てたときに興味を持ちました。そして2年ほど前に、勉強してみようと思い、学院に行きました。そして、教室の雰囲気を見て、その場で入学を申し込みました。
教室では、講師の先生がインテリアの表面的なことだけでなく、プランニングやデザインの考え方や具体的な方法まで、建築的な奥深いところまで教えていただきました。おかげで、インテリアコーディネーターから一歩踏み込んだ、建築の領域まで知ることができました。自分でプランニングしたり、デザインしたりできるのが楽しかったし、勉強していて飽きなかったですね。建築の基本的な考え方からユニバーサルデザインまで学ぶことができました。
試験勉強は、ひとつの問題集にこだわらず、たくさんの問題に触れることが近道だと思いました。学校からいただいた教科書も重要ですね。教科書にも出ていた基本的な問題が出題されていました。いろんな問題に触れて、わからないことがあると先生に尋ねたり、図書館や本屋さんで調べたりしました。
おかげで無事、一次試験は合格しました。今、12月の二次試験に向けて頑張っているところです。一次と二次を一気に合格するには、やはり、学科を勉強しているときから、余裕を見つけて二次の勉強もしておく必要がありますね。そうでないと、一度で両方を合格するのは大変なようです。せめて、論文だけでも一次試験と合わせて勉強していたほうがいいと思います。ともかく、12月に向けて、今から頑張らなきゃ、と思っています。


学校を卒業してから8年間、建築関係の会社で、マンションのモデルルームの飾り付けや、部屋の照明などお客様の相談に応じたりしていましたので、一次試験は自信がありました。
でも、それでも、過去の問題集を少しの時間を見つけては、1問ずつ丁寧に勉強しました。例えば、通勤の乗り物の中などで。ただし、二次試験は、苦手の製図などだったので苦労しました。一次に合格していれば、4度のチャンスが与えられるけど、3度目に合格しました。滑り込みセーフってとこですか。
これで、肩書きに信用もつきますから、あとは将来の夢である独立に向かって進めます。


短大を卒業する直前にインテリアコーディネーターのことを知って、関心を持っていたのですが、すでに就職が内定していたので、そのまま忘れていました。最近、そのことを思い出し勉強を始めたのはいいけど、本当にゼロからのスタートでした。
専門用語は全然分からないし、これでも短大時代は家政科で“住居学”を勉強したつもりだったけど、何にもなりませんでした。
だから、まず専門用語を覚え、毎日テキストを読み、3年間の覚悟で始めたのですが、こんなに早く合格するなんて、うれしいです。


実家が不動産と、建築関係の会社なので、以前から、興味は持っていました。それで、試験を受けることにして、毎日、1時間は、このための勉強に割くことにしたんですが、やはり、(試験の)時期が近づいたら、そんな余裕はなく、1ヶ月前から会社を休ませてもらいました。こんなわがままも、父の会社だったからだと思います。
父から名義上とはいえ、小さな会社の社長に任命されました。家のことも含めいろいろなことをすることになり、資格も取得して違った世界が待っていると思います。仕事の分野が広がりそうです。


家庭に入って時間が経ちますが、それまでは照明関係の営業の仕事だったので、製図も読めるし、ある程度のことは、それなりに理解していたつもりでした。
時間的な余裕もあり、これまでの、おさらいのつもりで、資格試験にチャレンジしたのですが、二次試験が気がかりだったので、学校の講座と先生の指導で身につけた知識と今までのキャリアを生かして、過去の問題集を中心にいろいろ勉強しました。
まだ、すぐに仕事につくことはないでしょうが、照明コンサルタントにでもなれればと思っています。


内装の仕事をしており、知識の蓄積はあったので、筆記の方は比較的楽でした。実技も、それなりに勉強はしていたつもりですが、試験に出る部分についてはよく分からなかったので、学校での勉強は本当に役に立ちました。
いまは特注の家具の仕事が多く、注文に来られる前に、すでに図面を引いて持ってこられる方もいますが、自信を持って、この部分はこんな色合いで、形もこうしたら、と自分の意見を大胆に伝えることができます。
以前に学院で2級建築士に合格していますし、つぎは宅建でも狙うつもりです。これも仕事の幅を広げるためです。


試験直前の1ヶ月は集中してよく勉強しました。1日3時間は勉強に没頭しました。
結婚する前は、住宅関係の会社に勤めていましたから、インテリアコーディネーターの仕事には特別な思いがありました。
ただ、パースの専門分野になると、難しくて、近寄りがたい一面もありましたが先生の指導で何とか合格する事ができてよかったです。
生活にもう少し余裕が出てきたら、幅広い視線でインテリア関係の仕事をしていきたいです。


学生時代の先輩が、インテリア関係の仕事で活躍していたので、将来、私も、と考えたのがきっかけです。
6年ほど建設会社に勤めていたせいか、インテリアコーディネーターに興味を持っていました。仕事もいろいろありますが、お客様に直接お目にかかって喜んでもらえる仕事って余り見当たらないでしょう。
勉強は、学校で教えられたものを徹底して復習しました。中でも、図面は、自分で毎日、応接間なら応接間と決め、何らかのレイアウトを頭で描き、自ら取り組んでいったのがよかったと思います。


子育てをやりながらの勉強でしたので、大変でした。昼間は育児で殆ど勉強できないので、家事をやり、子供を寝かせつけてから勉強を始めました。
主婦なら、外へ出かけることも少ないし、勉強がしやすいと考えて始めましたが予想以上に大変でした。
現場を知らないので、学科を勉強していても、もう一つ、ピンとこなかったのですが、先生の指導で随分理解できました。これで自信もついたし、今度は2級建築士に挑戦してみようか、と考えたりしています。


叔父が建築士をしていることや、私自身小さい頃から、建物や家具に興味があって、部屋の模様替えが好きでした。そんなことから、幼稚園の教諭をやめて学校に通いました。受験対策は、テキストや問題集が中心でしたが、丸暗記をするのが苦手なので、過去問で出題傾向をみるだけでなく一つひとつの問題を完全に理解するように努めました。学校の教材に触れたり、実際に使われている石材などを見にいったりもしました。
資格が取れれば、次は2級建築士にも挑戦し、建築やインテリアを総合的に勉強したいと思っています。